タバコが切れたんだ、寄ってくれよ、と言う俺の言葉を真に受けて、大介は集合場所のファミレスに続くルートを大きく外れた。大介にしてみれば、回り道。俺にしてみれば時間稼ぎ。
距離ってヤツはイヤなもんだよな。離れればイヤな時もある、好ましいこともある。近ければイヤなこともあるし、そっちの方が断然お得、ということもある。
だいたい、距離で計れるものにろくなモノはない。人間関係とか、時間とか、未来予想地図とか。
俺はだんだん、イヤになっていた。正確にはめんどくさくなっていた。無用な軋轢に直面したくない、という思いが強くなっていたんだ。
俺の思惑と、バンドのメンバーと、もちろん大介とも、すっかりずれていることは、少なくとも俺はわかっていた。
違いは、希望を持っているか、信じられているか、だと思う。
結局は、俺と智春の仲違いだ、というのが結論だろうが、その距離は、もう修復不可能になっている。と俺は思っている。
理由に明確なモノはない。ちゃんと言葉で説明出来るようになるには、時間がかかるだろう。
今する必要もないし、未来永劫墓の中でもいい。
でも、行かなければ、すべてが曖昧なままでいられる。俺にとってはそっちの方が、ずっと明るい未来だった。
ベッドの中で見られる夢程、甘美で優しいモノはない。どんな悪夢でも、現実よりはよっぽどマシだ。
正直それぐらい、俺の気分はすさんでいた。
こんな気分で、ファミレスなんてアットホームな場所なんか行きたくない。
それとは違った意味で、俺は場違いな場所にたどり着いた。
コンビニの駐車場に大介はクルマを乗り入れた。
俺は夜が大好きだった。でも、コンビニがそれを奪った。便利でなんでもあって、いつでも開いているのは、それは時間に追われた現代のサラリーマンなら、ありがたいモノだろう。
でも、夜は眠るモノだ。夢を見る時間だ。
その時間に起きているんだから、それがイイのだ。こんなに昼と変わらない明るい場所はいらない。
だから、風俗店のネオンは許せても、コンビニの蛍光灯は許せないのだ。
そういいながら、俺はこの便利なモノを便利に使っている。
そんなもんだよ。
大介ってヤツは、意外なところに気が回る。使命感がそうさせるのかもしれない。
誰がタバコを買いに行くかで一悶着あった。俺か大介かしかいないんだけど。
大介が買いに行かされると、その間に俺が闇に紛れて逃げる可能性がある。
俺が買いに行くと、そのまま店内に入らず、やはり逃げてしまう可能性がある。
二人で買いに行くと、やはり俺が逃げてしまう可能性がある。
いずれにしても、俺が逃げ出す予感が大介にはあったらしい。意外にヤツは敏感だ。
大介に買ってきてくれ、というと訝しそうな顔でまず最初の疑問を口にした。
じゃあ俺が行くよ、というとヤツは俺の方に手をかけて押しとどめた。
なんだよ、と若干の口論があって、結局二人で買いに行けばいいだろ?でも、それもアブねぇ、と。
最後には俺が一人で買いに行くことになった。
いざ逃げ出しても、車に乗っていれば直ぐに追いかけることが出来る、という結論だった。
俺ってヤツは几帳面なヤツで、いつでもタバコが切れても好いように、セカンドバッグにいつも余分を忍ばせておく。だから、俺は余分に一個、タバコを買うハメになった。
コンビニってところは、深夜にもかかわらず、人がいる。店員だけじゃない、ちゃらちゃらとしたお嬢さんとか、その付き添いとか、サラリーマンとか。間違った夜の楽しみ方を心得た人達だ。
俺はその中に紛れるように、買いもしないペットボトルを眺めてみたり、週刊誌をめくってみたり。そもそも、コンビニで買えるような漫画とか、雑誌とかに興味はない。ココにCG&CADマガジンは絶対に置いていない。溶接加工、という業界誌も置いてないし、サウンド&レコーディング・マガジンも置いていない。
ジャンクフードが最近のお気に入りだが、仕事の帰りにツマミながら運転して帰るのが一番旨い。そもそも、ファミレスにこれから行こうというのに、ジャンクフードもペットボトルも必要ない。
と、大介は思っているだろう、と俺はちらっとガラスの向こうを覗く。ヤツはじっと俺の方を睨んでいる。
緊迫しているんだよな。そう、この雰囲気がイヤなんだよ。
俺は簡単にその雰囲気、ってヤツに負けてしまう。こう見えても俺はひ弱なインパラのような人物なんだぜ。内弁慶、とも言うがな。
バンドのメンバーは、内弁慶の内、からは外れている。これはどうなんだろう?
中学からの知り合いで、間にブランクはあったモノの、もう五年も一緒に活動しているが、どうしても打ち解けない一線がある。たぶん、やつらも同じように感じているはずだ。
その見えない薄い膜ってなんだろう?
俺が独身だ、とか、唯一肉体労働しているとか、そのくせ音楽に湯水のように金を使っているとか、家に仕事を持ち帰るタイプだとか、ガンダムをよく知らないとか、上げればキリがないが、決め手に欠ける。
それが、俺の内に潜んでいるコンプレックスとか、そういう類のものであるのは、なんとなくわかっている。桜子を取られても、文句を言えない世界で数少ない人物達。あくまでも桜子が選べばの話だが。
そういうコンプレックスは、何処かで誰に対しても、俺は持っている。社会っていうモノとの付き合い方と言っても良い。俺は気軽にお嬢さんに声をかけるし、わりと無謀に話しかけていくタイプだ。と思われている。
でもそこにはちゃんとした計算があって、ある種のベクトルを持った空間で、そこに押し込まれた集団の中で、そういう特技が突出する、というだけだ。いわゆる、隣に座った女の子を好きになるタイプなのだ。
だから、全く見ず知らずの交差点の真ん中にポン、と放り込まれて、さぁ、未来の伴侶をそこから選べ、選ばなくても別に好いけどね、という曖昧な空間で俺はものすごく無力だ。計算に時間がかかる。時間が過ぎていく内に、チャンスを逃す。
そういう持って産まれたモノなのか、いつの間にかそうなったのかは知らないが、コンプレックスを醸造してきたんだと思う。
馴れ合っている間はイイ。でもそれがひとたび緊迫すると、コンプレックスは最高潮に羽を広げる。それならいっそ、常に緊張している間柄の方が、よっぽど訓練が進む。そうだな、軍隊とかに入れば、俺のコンプレックスは消えるのか?
とにかく、慣れ親しんだモノに、一番逢いたくないのが今なのだ。
でも、ウロウロと時間ばかり浪費するのにも限界がある。俺のポケットでケータイが震える。
大介が催促する。
俺は仕方なく、PeaceLightの声と共に人差し指を立てて、店員の愛想を受け止めた。
仰々しく、すっかり不健康の宣伝をするようになったタバコのパッケージを、指で弄びながら見つめていた。
車は本来の道へと急ぎ、DVDはメニュー画面のまま、軽やかなオルゴールの音を響かせていた。
手を伸ばす気にもならない。かといって、タバコの封を開ける気にもならない。
車窓に目を向けたくもないし、かといって見つめている先の小さな白い箱に興味が惹きつけられているのでもない。
とにかく、俺はただ、ここから逃げ出したいだけ。それが唯一、俺に残された希望。
でも、俺は護送されている。逃げだそうにも、チャンスは見つからない。後はただ、正直に、ゴネるだけしか手がない。
俺はこういう時、とても死を身近に感じる。死んじゃえばぁ、死んでやるよぉ、というお気軽で全く真実味のないモノだけど、死んだら楽になれるのかな、と漠然と思うのだ。
その茫漠とした空気の中に、何か光のような、やさしさを感じてしまうのだ。
俺は何度か、意図して、また意図せずに、その空気に吸い込まれそうになった経験もある。長い人生、バクチみたいな生き方をしていれば、そういうことだってあるサ。
でも、俺には確固とした死に対するイメージは湧かない。今と切り離された場所、すべてとの縁が切れる場所、っていうぐらい。
それはしがらみに疲れた時には、一番楽そうな場所だ。
でも、一方で、その楽な場所っていうのは他にもないのか?と気が付くのだ。
あるじゃないか、あるじゃないか、えぇ?
俺の部屋とか、少し前、そう少し前までは、バンドのやつらと一緒にいる空間が、それだったんだよ。
あぁ、そういえば、ストロベリー・クラブを始めてから、俺は死にたい、なんて思ったことはないな。
簡単にいえば、現実、っていうモノがあるとすれば、夢の世界がその反対側にある。それを旨く行き来することで、精神のバランスを取っていたって事だ。
バンドとか音楽とか、優しいお嬢さんの膝枕とか、友人との語らい?バイクで深夜の43号線をぶっ飛ばすとか?いずれにしろ、切り離された場所があったってコトだ。
でも、その実は最後の逃げ場所だったバンドが、今壊れようとしている。俺はふと、というかやっぱりというか、これは自分で壊したのか?と自問自答してしまう。
いつだってそうだ。俺はあまり他人に興味がない。すべては俺中心で世界が廻っている。半ば本気でそう思っている。
だから、誰かに抗いようのない理由で自分のテリトリーを犯されたり、壊されたりすることに、大きく反発してしまう。その反発がすべての俺の失敗の原因だと言っても良い。
それをよく知っていて、旨く折り合いを付けて、というのが現実に生きて流れていく普通の人なんだろう。
でも、俺にはそれがよくわからない。おかしいことを何故おかしいといわないのか?許せないことを何故許すのか?
イヤ、俺だって妥協してきた。今生きている、ココにいる、っていうのがその結果なんだけど。
結局その積み重ねは、自己嫌悪の連続だ。それは消えることなくずっと積み重なっている。
それはまさに怪物、名付けてジコケンオーが俺の背中を切り裂いて咆哮を上げている。いつだってその声に怯えながら、俺は虚勢を張るんだ。
その俺が、俺が、今他人にまさに俺自身を壊されようとしている。
それは誇大妄想かもしれないけど、俺はそう感じている。そう感じている以上、俺がこの状況を許せないのは、自明だ。
じゃあ?このファミレスに続く道というのは、いったい何なんだ?
死刑台に続く道なのか?それとも怪物ジコケンオーにエサを与える為のトロッコか?
俺は思わず、ごつん、と足下を蹴りつけた。路面を正確にトレースしていたタイヤとは違う振動が、車体に響く。
もちろん、大介はビックリした様子で、こちらをちらりと見た。
他人に壊されるぐらいなら、死んだ方がマシだ。
言葉にすればそんな簡単な言葉で言い表せられる、とても単純な感情が、俺の中で爆発した。それは未だ小さな爆発だったが、一度発火点に火が点いたモノは、もうどうすることも出来ないことは、俺自身が一番よくわかっていた。
ココで、ドアを開けて路面に飛び出せば、間違いなく怪我をする。もしかすると、後続車に轢かれて死ぬかもしれない。
でも、俺にはそれはなんだか陳腐に思えた。
それよりは、俺は未だ、負けない算段がある。
他人に壊されるぐらいなら、俺の手で壊してやる。
腹が据わった。といっても、未だ、緊張の極にある。決意がなんだか俺を紅潮させて、動悸を速めている。
どうやって壊すんだ?俺の一番大事なモノを、どうやって壊すんだ。バンドを解散するってコトで、それは終わるのか?
もっともっと、大きな何かを壊さないと、俺は自分の中の導火線の火がくすぶって終わるような気がした。
もう二度と、後戻り出来ないところまで、俺は跳びたいと思った。
それはいつか、背中のジコケンオーに食いちぎられることはわかっている。でも、今はそいつの大きな翼を借りることで、俺は今までになく自分の中で大切にしていたモノを壊すのだ。
それ以外にない。
これがまさに破滅型の思考能力だ。世の若いやつらがキレル、と恐れられているヤツだ。俺は若くはないがな。
どうしたって、道や大河を飛び越える時がある。閉塞した時にそびえる壁を飛び越えること。
言い訳のように、俺にはもう失うモノはない、と固く信じていた。
桜子も逃げてしまったし、バンドだって壊れてしまった。
あと俺に、何が残っているっていうんだ?
でも実は、そのいずれもが未だちゃんと壊れてはいないのだ。
それでも、俺がこの手で、自分の大事なモノを壊すことに昂揚し、唯一の希望を見出していた。
さぁ、これから、戦争が始まる。
雨は細いまま、フロントガラスを打っていた。ワイパーを動かす程でもない。
俺が蹴り上げた一発で、車内は一気に緊迫していたが、それをなんとも上手に見ぬフリをしようとする大介がいた。たぶん、ヤツは俺以上に緊張しているはずだ。
俺は一度覚悟を決めると、開き直るのは早い。簡単なことだ、今とは逆の場合を考えればいい。
新曲の発表でも、ライブの日程が決まったのでもイイ。俺は望んでバンドのメンバーに会いに行く。
逢って、最近どう?なんて話から、またバカ話が始まって、俺と智春が引っかき回して、鈴木が相づちを打ち、上島はただ、笑っている。そこへ大介が、そろそろ真面目な話、といって割ってはいって、ひとしきり事務的な話をする。その間も、俺も智春も何処かに端緒を探っている。話に糸口が見つからなければ、周囲に何か無いか?きょろきょろと見回す。それでもなければみんなの知らない日常で、未だ話していないことがなかったかを検索する。そして、話は脱線する。時間は過ぎるが、会話が終わることはない。距離感がなせる技だ。
そして、いつか何かのきっかけで、お開きとなる。だいたいが明日朝早いから、とか何とか。日常に帰っていく。
俺たちはそこで、茫漠とした寂しさに包まれる。こんなに楽しい時間が、終わるってコトを感じる。
手を振る、その刹那まで会話は途切れない。
でも、その寂しさを紛らわせるのは、仕事でもなければ、愛するの娘でもない。次にまた逢える、という未来だ。
それが希望ってヤツだ。その希望だって、いつかは終わるんだよ。でも、それが終わっていない内は、終わる瞬間まで信じていられるんだ。
少なくとも、それが今は、無い。
俺の中だけでも、それは潰えてしまった。
身勝手で、ただ、俺が考えたことだが。それも論法はさっきと一緒だ。
誰かが酷く重たい話を始めて、それが止まらなくなって、いつかは終わることを願っている。その先に、また元と同じような時間が続くことを望んでいる。たぶん。
でも、俺はその重たい話をしたヤツを、どうしても許せない。そうとなれば、仕返しの手痛い仕打ちは、希望をなくすことだ。
それをこの身をかけて、俺自身がもっとも愛して止まないモノを賭けて、俺はしっぺ返しをしてやるんだ。
自爆するんだ。そして、何処までも落ちていくんだ。
二つの道があって、そうではない一方の行く先を考えれば、心は落ち着く。そして同時に、ゴールも見えてくる。
あとは、いかにそのゴールにたどり着くか、だけの問題だ。
「やっぱり、行かなきゃなんねぇのか?」
「何処へです?」
分かり切ったことを、俺も大介も問いあっている。
「俺は、もうやつらと二度と会う気はない」
「・・・・そ、それは・・・」
どうとも応えられないことを俺は問い、大介も応えている。
「これで終わりでイイじゃねぇか。俺はまたバックレタ。あいつらは愛想を尽かす。それで・・・終わりだ」
「そんなこと無いですよ!時間はかかるかもしれないけど、また同じように元に戻れますよ」
俺がもう信じられなくなっていることを、大介は信じようとしている。もちろん、それになんの無理もない。俺が勝手に、そう思い込んでいるだけだ。誰だってそうだ。誰だってそうして、一番大事なモノを失うことを避けている。
「俺は昔、おまえに出逢う前に、ちょっとしたバンドをやっていたことがある。それを辞めた時に、自分にとってそのバンドがそれほど重要じゃなかった、っていうのもあるけど、それ以上に、俺には音楽しかない、ということが許せなかったんだ。そう考える程に、自分からバンドや音楽が変質してしまったことがあったんだ」
大介は黙って聞いている。
「それは間違いだと、気が付いた時にはもう遅かった。でも、俺はそれはそれで仕方のない遠回りだと思った。だから、気が付いてからはずっと、音楽から離れたことはない」
俺と大介が出会ったのは、ちょうどその頃だった。
「今でもその思いは変わらない。でも、それが俺たちである必要はないんだよ」
「でも・・・わざわざ今あるモノを捨てて、新しい何かって・・・そんなものあるんですか?」
大介の問いは、辛辣だった。俺はその答を持っていない。でも、だからこそ、希望があると信じている。イヤ、今は信じ込もうとしている。
その為の儀式なのだと、俺は気が付いた。
「いずれにしろ、俺の中ではもう、終わったことだ」
沈黙が流れた。大介は黙々とハンドルを操作した。
やがて、運命の処刑台に俺たちは着いた。
大介はエンジンを切ろうとしない。俺も、外に出ようとはしない。何故か、俺たちの間に、その儀式は共通認識と言うべきものになりかけていた。
「話し合えばいいことでしょう。アレからちゃんと、向き合って話したこと、一度もないじゃないですか?勝手なことを勝手な時間作って、好きな場所で言い合って。それじゃなんの解決にもならないですよ。俺たちは四人でバンドなんじゃないですか?何かトラブルがあったら、四人で解決すればいいじゃないですか。それをなんでこんなに・・・」
そんな簡単なコトじゃないんだよ、と言いかけて辞めた。たぶん、大介のいっていることは正論だ。誰にも反論の出来ない、至極真っ当な意見だ。
でも、それはたぶん、俺が思っている音楽というモノとの関わりの中で、通用するモノじゃない。音楽がそうされるんじゃない。俺と音楽との関わりが、必然的に俺にルールを見せているんだ。
今回は、そのルールからは逸脱している。少なくとも、俺にはそう見える。
だから、他人のルールがそこに存在しているのは、確かなことだ。
それが俺のコンプレックスの原因でもある。こういう時に従うルールが違うのだ。
それは肯定されるモノでも、否定されるモノでもない。
ただ、一緒には歩いてはいけない、ということだ。
手を繋ぐには、犯してはならない一点を超えてしまっているんだ。
たとえ俺が、そのルールのせいで、世界から孤立しようと、俺は自分というモノを信じていたい。
大介は、何か言いたそうにして、言葉にならなくて、もどかしい時間を飲み込んだ。
そして、諦めたように、ポン、とハンドルを両手で叩くと、俺の方を向いた。
「哲也さんの口で言ってください。俺には説明出来ないですから」
そうだよな。大介、おまえまで、俺とは違うルールなんだからな。
「じゃぁ、呼んできてくれよ」
自分で勝手に行けばいい、と言いたげなところをグッと堪えて、大介はクルマを降りた。未だ、ヤツは、希望ってモノを捨てていない。それは人間として大事なことに違いない。
でも、俺にはそれは出来ないんだよ。俺にそれを出来る気概があれば、俺はそんなに苦労しないで済んだだろう。
俺は暗闇の駐車場の中を、一直線に歩いていく大介の背中を見つめていた。クルマのセールスマンである象徴のように、仕事帰りの白いシャツがまぶしい。
その白が、ファミレスの看板が放つ暖色に染まって、大介は入り口の前に立った。ドアを開けながら、こちらをちらりと見た。
というより、睨んだ。
サヨナラは用意されている。その席はちゃんと手招きをしている。
大介とも理解し得ない、という条件付きなのか。
手持ちぶさたに、俺はDVDの画面を切り替えて、TVのチャンネルを換える。こんな時間に、何をやっているかよくわからない。当然、見たい番組なんてモノもない。
ふと、俺はまた明日、休日出勤するのかな、なんて事を呑気に考えた。
仕事、っていうモノにまるで現実感が湧かなかった。それよりは、この今まさに起ころうとしている夢の終焉の方が、ヒリヒリするぐらい現実にベットリとまみれていた。
殴り合いとか、そういう身体に直接感じるような、痛みの方が、現実感は強烈なのだろうか。目が覚めると人はよく言うが、そういう暴力とかとは無縁の生活を送る方が、人間的なんじゃないのか?物わかりの悪い子は殴ってでも、って子供のいるやつらなら、本気で信じているのかもな。
殴れば、その一瞬で済むから、なんていうから、心の痛みが覆い隠されてしまう。殴れば殴ったヤツが悪いのだし、殴られたモノが弱者だ。でも、心の勝ち負けや、痛みは誰も推し量ることが出来ない。
そしてそういう時だけ、人は理性を持ち出す。文明を持ち出す。理念とか、信条とか、めんどくさい話をする。
身体の痛みや傷は、直すことが出来る。同じように心の傷もいつかは癒える。
なんて、本気で信じているヤツがいるんだろうか?そんなのはまやかしだよ。
俺が智春を傷つけたのなら、ヤツは一生俺を許さないだろう。許したとしても、一生忘れないだろう。忘れたとしても、この時間を無かったことには出来ない。
つまり、躓いた瞬間に、未来は決まる。だから躓かないように人は注意する。
何か言葉を発したり、行動を起こしたり、それが時間や空間の元で行われたことである限り、それは全くの無に帰することはないんだ。
人はいつまでも、死のその瞬間まで、決断を下し続けて生き続けるんだ。
明日も今日と同じ、平穏無事を選択して、激しい決意と共に眠り、朝目覚めるんだ。
そうして日常は流れていく。ダラリロユラリンと流れていく。漂うだけで、人は歳を取る。
楽な人生だ。
俺は誰かの為に、何かをしたいとは思っても、出来ると信じてはいない。たとえ桜子にしたって、出来ることは限界がある。いつの日か子供を持ったとしても、限界がある。
だから、俺はその責任からは逃げたくないんだ。責任が取れないなら、早々と逃げ出す方がイイ。触らない方がイイ。
でも、触れろ触れろの大合唱だ。大介を先頭に、ぞろぞろと大の大人が三人、こっちに向かって歩いてきている。
俺の中で、何かが大きく弾けた。俺はその衝撃的な音を、ハッキリと聞いた。
助手席に座る俺の扉一枚向こうに、大人達が居並ぶ。みんな複雑な表情で俺を見据えている。
俺はウインドウを下ろした。すぅぅぅぅっ、とガラス窓は降りていく。
湿った空気が流れ込んできて、アスファルトに残った熱気が不快感を助長する。
「降りないのか?」
いつになく、上島が口を開いたのには、少し驚いた。でも、考えてみれば、一番理に適わないことを嫌うのは、上島かもしれない。
「降りて話すまでもない。答はもう、決まっている」
そういい終わらないウチに、俺は胸ぐらを捕まれた。突然のことに、俺はまた驚きを隠せなかった。
掴んだのは、鈴木だった。体育会系の悪い癖だ。
俺は鈴木の手首を掴んで解こうとした。だが、柔な俺の力ではどうすることも出来ない。
替わりにそれを押しとどめたのは、上島と大介だった。
コイツ、殴らなきゃ、と離されながら鈴木は上気した声を出した。
代わりに、まるで目の前のカーテンがすっと開かれるように、俺と智春が目を合わした。
鈴木の一連の動作を、ヤツは見るともなく見ていながら、実は俺の方を直視していた。
たぶん、ヤツは俺がどうするつもりか、そして、何故ココでじっとしているのか、理由を一番理解しているはずだ。
それが今までの信頼ってヤツで、そして今、一番の大きな壁の原因だ。
智春は、吸いかけのタバコを、何度も何度も口に付け、時折鈴木の方を見ていた。
俺と智春が対峙したことで、鈴木も上島も、大介もそれを遠巻きに見ているだけだった。
俺はなかなか言葉がでなかった。それは、たぶん、言葉より、台詞を探していたんだろう。そんな唄があったな、と俺は考えていた。
「辞めるのか」
問うたような、確認するような、感想を述べるだけのような、小さく短い言葉だった。
言い終わって、タバコをポトリと落とし、靴底で踏みつぶす。
「それは、おまえが望んでいたことだろう」
俺はどうも、一番辛らつな言葉を返したようだ。今まで見たことのない、たぶん女性の前で一度も見せたことのない、きつい目つきで、智春は俺を睨んだ。
この場で、俺も智春も、絶対に言えない一言があった。
それは許す、ということだ。
ある意味、俺たちにとって一番必要なその言葉と、俺たちは一番遠いところにいる。
互いに自責の念はあるだろうが、それが今に至る過程をさしているのか、その前のずっと長い長いつきあいをさしているのかはわからない。
でも、俺たちは、互いに傷つけることでしか、今はこの場を収められないでいた。
イヤ、それは俺の思い過ごし、かもしれなかった。
智春は俺よりももっともっと、人間関係に優れたヤツだ。でないと、一流企業で営業なんかやっていけないだろう。こっちが謝ってしまえば、見て見ぬフリしてしまえば、コトが丸く収まる、ということを一番よく知っているヤツだ。
あくまでもこれは、俺の偏見でしかないがな。
だからこそ、俺たちは思惑は違っていても一緒にバンドをやれたんじゃないのか?
俺はいつも導火線だ。誰かが望む場所を提供する。その場の中で、誰かが望みを叶える。
言い出しっぺで、賑やか師の、それが存在意義だ。利を得るのはいつも他人。
それに乗っかって、俺も乗っかられて、それで幸福だったんじゃないのか?
俺が作る場所は、見かけは甘美で、それこそ夢の世界だ。おまえは思う存分ギターを弾きたいんじゃないのか?大勢の女の子の真ん中でサ、キャーキャー言われながら練りに練ったギターソロを聴かせてやるんだ。
俺はそれが自分に向けて発せられた歓声じゃないことを知っていて、同じバンドだから、っていう言い訳を携えて、その気になっていたんじゃなかったのか?
現実はまぁ、その十分の一にも満たないかもしれない。ステージの一番前で踊っているのは、おまえの長男だし、後ろで控えているのは顔見知りの連中ばっかりだ。せいぜい対バンの客が、申し訳程度の拍手をしてくれるだけだ。
でも、それが俺たちにとっても精一杯の夢だったんじゃなかったのか?
おまえも俺もその領分を逸脱したんだ。
望むと望まぬとに関わらず、そうなっちまったんだ。それも、お互いのすれ違いでな。
「終わりだ。解散だな」
「それで好いのか?」
智春にしては意外な問いかもしれなかった。大介と同じように、未だ希望を何処かに見出そうとしているのか?
おまえらしくないよ、と言いたかったが、それほど今の俺はフレンドリーにもなれない。
「終わりだよ。それで好いだろ?」
駄目押しだ。十年間紡いできた夢が消える。
別に、俺たちが解散したって、明日何かが変わるとは思えない。日常に戻るだけだ。
でも、それが少なくともココで面付き合わせている5人には、何か大きな損失になるのだ。
そして、それは俺の勝手な思いこみなのだ。
日常に帰れないのは、たぶん、俺だけだ。
もっとも大きなズレは、たぶんそこだ。俺が賭けているモノ程、智春にも鈴木にも上島にも、そして大介にも、大きな存在ではない。戻った日常で、それなりにやっていけるのだ。
俺はそう思った瞬間、いいようのない怒りに襲われた。
俺が紡いだ夢が、俺だけのモノだった。おかしな話だが、それがとても許せなかった。
俺たちは別に今更スターダムにのし上がろう、なんて事を夢見たわけではなかった。俺たちは俺たちでずっといつまでも続けていこう、この楽しい時間をずっと守り続けていこう、それが何より大事なことだったはずだ。
でもそれを夢想していたのは、ただ俺だけで、他のやつらには帰る場所があったのだ。
イヤ、俺にだって帰る場所はあるのかもしれない。
だけど、俺にはそれが想像出来ないんだ。辞めると言いだした俺がいうのも変だが、一番音楽とは切っても切れないのは俺なんだよ。音楽しか能のないヤツなんだよ。
俺はその真実ってヤツに、酷く憤慨していた。
「終わりだ。終わり。全部終わりなんだ。何もかもが終わるんだよっ」
俺は駐車場に響き渡る声で叫んだ。それは、誰の元へでもなく、俺の耳の中だけで幾重にも重なって、響き続けた。響きの波が襲う度に、俺は自分がドンドン追いつめられていくのがわかった。
自分が賭したモノが、俺を苛んでいる。
俺を馬鹿だと叫んでいる。
嘲笑っている。踏みつけている。
俺の背中のジコケンオーが咆哮を上げている。俺の鼓膜を食い破り、胸を引っ掻き、足下を蹴り飛ばしている。
ヤツが俺に取って代わる。そんな恐怖にも似た、戦慄を俺は感じていた。
明日は仕事に行けないどころか、俺は音楽すら出来ないんだ。
俺の叫びに弾かれたように、鈴木がまた、俺の元に跳んできた。廃人の胸ぐらを再び掴んで、窓から引っ張り出そうとした。
大介と上島が必死でそれを押しとどめる。
鈴木は何をそんなに激しているんだろう?俺の方がおまえよりもっと酷いんだぜ。
おまえにはちゃんと帰る家があり、帰る家庭があり、ちゃんと理性が月曜日になれば仕事に向かわせてくれる。月末には給料が振り込まれて、毎年二回のボーナスで家でも建てるんだろう?
それで好いじゃないか?それに邁進出来るなんてなんて素晴らしいことなんだ?
俺には、もうそれもないんだよ。俺にとって生活や桜子や仕事なんて、バンドをやる為の方便にしか過ぎないんだよ。場つなぎ、退屈しのぎなんだよ。それは帰る場所にしちゃ、まるで貧祖じゃないか?
「大介!」
智春が叫んだ。激した鈴木と、俺を引き離す為に、今すぐここから立ち去れ、と支持する。なんとも冷静な対応だ。
さすがだ。大人だよ。
鈴木が怒っているのは、プロセスだ。プロセスはすなわち男気とか、筋を通すとか、ヤクザの世界でまかり通っているモノだ。この際、結果が同じなら、どういう道を辿ったにしても一緒のことだぜ。
おまえも智春と同じように、冷静になれよ。おまえの方が取り分は多いはずだよ。
鈴木に引っ張られながら、俺は半ば呆けたようににやけていた。と自分では思っていた。
智春も加わって、鈴木を俺から引っぱがすと、大介は運転席に乗り込んだ。
エンジンをかけっぱなしのクルマのギヤを入れる。ミラーを確認して、三人が離れたことを確認してから、クルマをスタートさせた。
大介、おまえも相当に冷静だよ。イヤ、この場合強か、っていうのか?
いずれにしろ、みんなポーズを付けてこの場を収めただけに過ぎない。
時間は続く、夜は明ける。明日になれば、少し時間をおけば、また良い方向に向く、なんて希望を持っているんじゃないのか?
あぁ、嘘偽り無く、俺もそう思っているよ。イヤ、思っていたい、と思うよ。
でもな、無理なんだよ。俺は頑なになることに、自分の未来を賭けたんだ。二度と戻れない場所を作ることで、次の新しい場所へ進む推進力を手に入れようとしているんだ。
それがな、破滅型の美学ってもんだよ。
車はタイヤを鳴らして道路へ滑った。黄色信号を突っ切って、ファミレスはアッと言う間に闇の向こうだ。
あれほど望んだ、距離が遠くなる。遠くなる。
でもなんだ?この失望感というか、虚無感というか、やるせなさは?
本当に俺は、ココでこうしてこうすることを、望んでいたのか?
もうあとは、墜ちていくしかないのか?墜ちていくしかないのか?墜ちていくしかないのか?
まだまだだ。
俺は未だ最低にはなっていない。最低に辿り着かないと、未来への推進力はくすぶったまま、航行能力を失ってしまう。道の真ん中でエンストなんて、一番情けないぜ。
ちくしょう、何をしてやろう?何をしてやろう?何をしてやろう?
仕事を辞めるか?その程度なら、今までだっていっぱい繰り返してきたよ。
桜子?ヤツだって、とっくの昔に離れていったよ。
あとはなんだ?他に辞めるモノはないか?辞めるモノはないか?辞めるモノはないか?
帰って曲のデータの入ったハードディスクを粉々にするか?あんなモノ、いつでも再生出来る。
何がある?何がある?何がある?
俺は全開にした窓から吹き込む風をものともせず、声を出して笑い続けていた。
訝しそうに、大介は俺の所業を見ていた。呆れていたのかもしれない。
でも、俺はそれでも笑うのを辞めなかった。
「落ち着いてください」
俺がDVDの音量を上げて、車内が大泉洋や藤やんの声に満たされる前に、その手を大介が押しとどめた。
俺は反射的にヤツを睨んだ。今はハッキリと呆れているとわかる顔で、大介は俺を見ていた。
静かに澄んだ瞳が、まるで憐れんでいるようだ。
憐れんでくれてけっこう。俺はもう、引き返さない。
「なんかもう・・・哲也さん・・・今日は変ですよ。解散なんて・・・そんな・・・」
大介は静かに道端に車を停めた。いつの間にか、海に面した整備された歩道沿いに、俺たちは紛れ込んでいた。
クルマを停めると、波の音が聞こえた。暗闇の海を見渡すと、遠くに漁船の灯火が見えていた。
動きが止まった途端、大介の中から迸るように、感情が溢れ出てきたようだった。だが、それは綺麗な言葉や、ちゃんとした声にはならず、俺には半ば嗚咽のように聞こえた。
俺はそっぽを向いて、海を見つめる。タバコに火を点け、その明かりだけが、俺の顔を照らす。
一体俺は今、どんな顔をしているんだろう?
金曜日とか、土曜日とか、夜になればここら辺は、一晩の恋人を求めてクルマが居並ぶ。多分、何処かでそれは並んでいるんだろうが、少なくともココではない。
そういう場所に、大介が意図して連れ込んだのか、それとも偶然なのか。意図していたんなら、大介は俺の想像をはるかに超える、偉大な人物だよ。
そういう後先見分けがつかないところを、俺は初めて見た。自分がいつもその立場で、客観的に見る、なんて機会が極端に少ない、というのもあるが。
「本当に、解散、なんですか?」
大介は、本当に無念そうに声を出した。絞り出すように、ちゃんと相手に届くように。
「その通りだ」
多分、とか、おそらくとか、曖昧な言葉ではなく、俺は断言した。それは十中八九、自分に言い聞かせる為だ。
それは反省からなどではない。閉塞した状況を突破する、唯一の方法だとも思わない。
ただ、俺がその未来に賭けているだけ、というのも今では陳腐すぎる。
もっと深い底で、憎悪がある。何かに対して、俺は憤りよりも、憎しみを感じている。
それは大部分が、自分に向けてだろう。
俺は人が言う程楽天家でも、お調子者でもない。もっともイヤな部分を、一番知っている人間だ。そういうヤツは、実は他人を嫌悪させることについては、天下一品だ。楽しませることよりも、毛嫌いさせることの方が得意だ。
でも、そんなことは誰も望んでいない。俺だって、一人残らず自分以外の誰もに、チヤホヤされたいと思う。
それが出来ないヤツもいるんだ。それが俺だ。
俺に近づいてくるヤツっていうのは、それを乗り越えた、ある意味冒険者だ。
いくら愛想が良くても、そんな仮面はそのうち剥がれる。そして誰もがうんざりする。
でも、それを押して、その理由はわからないが、乗り越えてくるヤツだけが、俺と行動を共にする。
そしてやがて、みんな疲れてしまうんだ。
ついに、その残り少ない理解者も、離れていく結果になるんだな。
俺が覚悟しないといけないのは、音楽は一人でも出来る、って事だ。別に人前で歌う必要はない。自分だけが楽しむだけでもイイ。他人との接触を一切閉ざしても、音楽は出来る。
俺はそっちに賭けたんだ。そのことを確かめたい、と決めたんだ。
そういう人間嫌いの選択肢を選んだ俺、それがもっとも憎むべき相手なんだ。
諍いは誰でもある。人間が二人いて、それが男でも女でも、言い争いは必ず用意されている。親兄弟親戚縁者、そういう間柄にだってある。
でも人は妥協して、その関係を維持する。維持しようとする。
俺はそれをしないだけだ。切れてしまうモノは、じっとその事実を見ているだけだ。
時が過ぎれば、それは悲しみさえも乗り越える。そのことを俺は知っている。
傷や痛みが見えなくなることも知っている。そういうフリが出来ることも知っている。
でも、そこに無理が生じるのだ。その無理が許せないのだ。
無理するぐらいなら、そういう状況に、追い込まれたり追い込まなきゃイイじゃないか、と思う。
誰が追い込んでいるんだ?それで俺は他人を憎むのだ。
そして、それを知っている俺を、嫌悪するのだ。
「実は、哲也さんには言わないように、って頼まれていたんですけど」
「誰に?」
「みんな、にです。俺が直接聞いたのは鈴木さんだったんですけど」
大介も、タバコをくわえて、火を点ける。ようやく、ひとまずは落ち着いたようだ。
「みんな、今回の件が、すれ違っちゃって袋小路に行っちゃっているって思っていました。何か言うと、どうしてもそこへ追い込まれてしまうような、そんな気がしていたんですよ。それで、まぁ、今回の件は、いろいろあるけど、顔さえ合わせて、ちょっと話しているウチに、元の通りに戻そう、なんて思ってて、それで、前回のミーティングにこぎ着けたんですよ」
ふぅぅぅぅっ、と大介は煙を吐き出した。フロントガラスに煙が当たって、左右に広がる。向こうの工場のライトがその陰影を灯す。
「鈴木さんが智春さんを説得する、っていう事になって。ただ、哲也さんは逃げないだろうって。というか、信じていた部分があって、やっぱりこのバンドは哲也さんがいてこそのバンドだし、っていうのはみんなわかってましたから、どんなことがあっても修復は出来るだろう、って」
俺は未だ、海の方を見ていた。大介の言葉を理解しながら、その意味をなるべく単純に捉えようと思っていた。
「変な言い方ですけどね、もうバンドっていうモノとは、もっと違う、俺なりの考えですけどね、家族みたいな、もう一つの家族みたいな、そんな感じがしていて、それで、みんな信じ合っているって思っていたんですよ。俺だけじゃなく、上島さんも同じコト言ってました」
家族、か。そういえば、俺には、家族っていうモノにイイイメージがないんだよな。
俺のオヤジは昔から気に入らないことがあると、直ぐに酒を飲んで暴れた。俺が早々に家を出て、妹も早くに結婚を望んだのも、それが大きな理由というのもあながち嘘ではない。自分で酒を飲むようになっても、妹が長女を産んでも、俺にはオヤジっていうモノを許容出来なかった。
いろいろと考えて、ちょっと精神をおかしくした時もあった。いつも自分というものを見つめる時に、行き止まりになることがある。その原因がわからずに、もどかしく自分を傷つけ続けたこともあった。
最近だが、俺はそれをオヤジの姿に見出した。オヤジは俺に、どうしようもない劣等感を植え付けたような気がする。
誰にもコンプレックスはある。だが、俺は幼い頃から、オヤジと酒、という関係の中から、何か怯えていた。それを家の中だけの事情にしようと躍起になって、他人には絶対に心を開けなくなっていた。
小さい頃、俺は酷く感情の乏しい子供だった。嬉しいとか、特に悲しい、ということに鈍感だった。こういう時に人は嬉しいって思うもんだな、とか、悲しくて泣いてみせるモノなんだな、とか、そういう風に考えていた。感情が自分を支配していても、何処か冷静だった。感情は一瞬で、後は理性で片付けられる子供だった。
それが年を経るごとに、酷くなり、そしてその反動で、他人に対して物怖じしなくなり、他人になんでも心を開き、そうすることで、今までになかったモノを取り戻そうとした。
そう、俺にとって、家族っていうモノは忌避するモノで、だから他で家族っていうモノを求めていた。
理想の家庭っていうヤツを、そういう幻想を、代替するモノだから夢として確固たるものとして据えることが出来る。
それがお嬢さんとのつきあいであり、バンドであった。ような気がする。
でも、いつも気が付くのだ。特にこういう、それが夢だよって、潰えた時に。
家族っていうモノは、もっと醜悪なモノで、いつかは逃げ出すモノなんだって。
「でも、俺は逃げた。そして、このザマだ」
「そんな風に言わないでください。でも、確かに、裏切られたっていう思いはしました。哲也さんに限って、って」
ふん、と俺は鼻で笑った。悪態を突く、俺の悪い癖だ。本当に悪いヤツは、悪態など突かない。
「それにあの日、実は桜子さんが来ていたんです」
俺はその大介の言葉に、初めて動揺した。自分の中で怒りが充満して、でも何処かで冷静を装っていても、思いも寄らないところから突かれると、やはり弱さを露呈してしまう。
桜子とバンド、二つとも大事なモノ、だった。かつて、という前提が着く。
だが、それはもちろん触れ合うところがないわけではないが、明確に分かれてもいた。それは変な言い方だが、バンドも趣味に過ぎないが、仕事未満趣味以上、っていう曖昧なモノで。でも、桜子はプライベートで、音楽とも仕事とも混同してイイモノとは思っていなかった。
でも、だから、何故そこに桜子が?
「智春さんが、連れてきたって言ってました。桜子さんが、なんとか関係修復を、っていうんで智春さんと連絡付けたみたいで」
確かに、と俺は妙に納得して、そして同時に深い谷底に突き落とされたような、そんな気分だった。それは、本当に思いもよらないところで、俺のワガママを笑われているような、そんな気がした。
桜子のメアドは、大介を含めてバンドのメンバーならみんな知っている。同様に、メンバーのメアドも電話番号も、桜子は知っている。
俺が教えたわけではない。それを促しはしたが、それぞれと一対一で交換した。全部俺の目の前で、だった。
でも、それをどう使おうが、それは桜子の勝手であり、メンバーの思惑次第だ。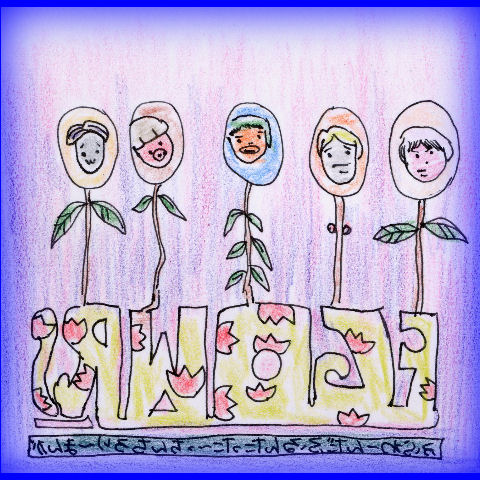
何度か、例えば鈴木と智春と桜子で飲みに行ったり、メールを交換したりとか、そういう話はちゃんと聞いていたし、別にそれをとがめる必要もないと思っていた。
表面上はそうだから、それに対して俺が何を言うこともない。それは別に冷静だからとか、言い訳だからとか、そういうモノでもない。純粋に俺の友達と桜子が仲良くするのは好いことだし、お互いがもう大人なんだから、他人がとやかく言うことでもない。
でも、噂は噂だ。それが真実かどうか、確認しようとも思わないし、したところで、相手が智春なら、仕方がないと思うしかない。
そうやって、俺がいつの間にか頭の中で処理済みのことが、これまた変な所でその境を曖昧にして、複雑に絡み合っている。俺が望んでもいない所で、俺の知らない所で、何かがまた俺を玩具にしている。
俺の憤慨は、智春と桜子の関係に対してではなく、その曖昧な、あずかり知らない所で変質する現実に対してだ。
俺は今回の解散の決断だって、さっきのファミレスの所業だって、ついさっきまでの大介との会話だって、全部俺自身がコントロールしている、少なくとも俺自身は俺がコントロールしている、という自負があった。そうでなければ、俺はせっかく見つけた俺だけのモノを、他人に委ねてしまう、という失敗を犯すことになる。
だが、それよりも現実のスピードというか、実態の複雑さは形容しがたいのだ。俺の手の平では、全く小さすぎて想像の範囲を超えている。
それは何より、俺に無力、という二文字を押しつける。
俺にとって、それほどの屈辱はない。
自分のことさえ、自分でどうにもならないこと程、愚かなことはない。
だが、大介の口は、そんな俺の意図とは別の所で、喘ぎ喘ぎしながらも、真実を告げていた。
「桜子さんまで泣いてましたよ。哲也さんがいつまで経っても現れないから、もう、心配というよりも、桜子さんを見て、ちょっと怒ってきたっていうか、俺たちを心配させるのは別に好いんです。つきあいも長いし、そういう突飛な所を理解出来ないワケじゃないから。でも、桜子さんを泣かせちゃダメですよ」
お嬢さんの涙は核弾頭三個分だ、と最初に言ったのは智春だ。今回、そういう思惑があって連れてきたのかどうかはわからない。多分、そんなことはないだろう。
でも、すっかりペースは智春と、桜子に乗せられた。そこに居合わせなかった俺までも、周り廻ってペースに乗せられたことになる。
俺は未だ憮然としていたが、心の隅では意気消沈していた。フッと何かが事切れる感覚。それを必死で押しとどめようと、せめて表情だけは憮然としようとしていた。
自分の中でついさっきまであった、俺を維持し続けていた怒りを思い出そうとしていた。
あの昂揚した、ちゃんと理由があって、納得がいって、俺の中でできあがったストーリーのある怒りを。
そうでなければ、俺は今にも泣き出しそうだった。
変な言い方だが、負けたんだと思った。
今となっては、俺はあのミーティングに行かなくて良かった、とホッとすることになる。智春と桜子が現れる場面で、俺は冷静でいられるだろうか?瞬時に判断を下すことが出来ただろうか?
少しでも遅れていくと、今度は泣きじゃくる桜子を宥めるみんながいて、その中で俺は笑顔を引きつらせることになる。
計画は結果オーライで、そして俺の失敗は用意されていた。その場を収めても、きっと後で爆発したはずだ。そして混迷はもっと酷く、深く、しこりとなっただろう。
それもこれも、全部桜子と智春が仕組んだような気がする。俺の勝手な思いこみだが、俺がそう思いたがっているのは、俺自身がよくわかっている。
俺は引き裂かれた自分の思いに、未だ収拾が付けられないまま、それをかき消すように叫んだ。
「もうイイよ」
大介が、唖然とした顔で俺を見つめた。
「終わったことだ、今更何を言っても、答は変わらない。それでおまえも好いだろう?」
「それならちゃんと理由を説明してくださいよ。何故捨てるんですか?せっかくのバンドじゃないですか」
「説明して、説明出来るモノじゃないし、聞いてわかるものでもないんだ」
「やっぱり智春さんですか?智春さんの方が謝れば好いんですか?」
「もう、そういう問題でもないんだよ。とにかく、今日は帰してくれ」
「俺にも言えないんですか?」
言えないんじゃない。言っても納得させられないだけだ。それは多分、正直な俺の気持ちだ。
そう、納得させることは誰も出来ないんだ。
ずれてしまったモノを分析は出来るだろうし、そこから導き出せる答もあるだろう。
でも、それを放棄した所で、この答はある。それは言うなれば、俺の直感であり、ワガママだ。
それが他人を納得させられない以上、それは間違っているのかもしれない。
だからといって、決断が無効になることはない。俺は唯一、みんなに納得させられるモノが、解散、という現実だけなのだ。
俺はミックにはなれなかったし、結局「スティール・ホイールズ」も作れない。見回してみても、ジェフ・ベックは居そうにないし、見つけるのももどかしい。
だから、俺には、今は何も言えない。そして、俺は早く、誰もいない所に帰りたいのだ。
結局帰る場所にしてはおぼつかない場所でも、そこなら、自分一人になれる。これからの第一歩にとって、ふさわしい場所がある。
俺は無言で、じっと大介を見つめた。
大介は口を開けたまま、何か言いたそうにして、やがて、うなだれた。ハンドルに額を当てて、しばらくして、顔を上げた。
大介はDVDに手を伸ばした。イキなり大音量で、藤やんの笑い声が響く。重なるようにうれしーの声。
「大泉さん、語彙力が豊富」
静かにクルマは歩道を離れた。
マンション脇、階段の直ぐ前で、大介はクルマを停めた。ドライブスルー並みに効率の良い停め方だ。
あれから20分程、オレはそっぽを向いたまま、大介も何も喋らなかった。希望をなくした空間。
オレはドアを開け、外に出る。いつもなら、ありがとよ、の捨て台詞のひとつも吐いて出るが、今日は何も言わない。背中で語る男。
大介も、何も聞かなかったし、今度アレしますんで、という愛想笑いも無しだ。また連絡します、というのが本日最善のサヨナラだろうが、それは多分、大介の中の怒りが押しとどめたに違いない。
今日、俺たちは誰もが例外なく、怒りに満ちている。それもよく考えればおかしな話なんだがな。
オレが少々荒めにドアを閉めると、大介はたちまち闇の彼方へと車を飛ばしていった。
俺はその後も追いかけず、階段に足を踏み入れた。
今思えば、その時、オレと大介の関係性だけにしか興味がなかったのが、多分最大の今日のミスだ。やはり、俺は冷静さを欠いていた、と言わざるを得ない。
俺は自分の部屋に帰ることが出来たことに、正直、満足していた。というか生還出来たことに、素直に喜んでいた。
心の中では、怒りがくすぶり、興奮が渦を巻いている。このまま寝たって、単純には寝られそうにもない。言葉や台詞や場面が洪水のように襲ってきて、俺の動悸は静まることがないだろう。身体は疲れているんだけどな。
階段はコンクリートせいで、底のツルツルになったトレッキングを履いているので、音はしない。
俺はこの階段に足を踏み出すたびに、もう自分の部屋を思い描いている。
実のところ、俺に家族、という意識は希薄でも、場所を求める求心力は強い。
誰かと形作る空間ではなく、その場所そのものに横たわっている、自分のルールしか存在しない、足場が恋しいのだ。
道を歩いていても、仕事をしていても、自分の足下が自分のテリトリーだ。そこを犯されるのは、正直、気分が悪い。
でも、その種は、ただ突っ立っていると、容赦なく俺に襲いかかってくる。それが煩わしい。
俺は俺が信じるルールで、世間と繋がっていたいと思う。自分が信じる正しさで、世の中の洪水を泳ぎ渡っていたいと思う。
思えば、さっきまでそこにあったバンドだってそうだった。俺が信じるルールが、全部ではないにしても、そこにあったはずだ。あったと信じてきた。
ただ、バンドが解散したことに、裏切られたという気持はない。俺がその決断をした、という納得ずくのモノだからというせいもあるが、それよりもやはり俺は、プロセスがただ、信頼の形を見せてくれただけなんだと思う。そして、それはそれが何処か違う、と感じて、判断して、そして拒否しただけだ。
少なくとも、今は俺は、自分の部屋に帰るしか、肯定出来ない。俺の部屋は、家賃を払っている限り、俺を拒否することはない。
それは嬉しくもあり、ただ、今は少し残酷なような気もする。そこにしか、俺は居場所がないのが、心細く感じる。自分の足下以上に、それは心許ないことに感じる。
そして、そこにしがみついていることは、許されないのだろう。
でも、今の俺に必要なのは、ベッドで自分の夢を見ることだ。
だけど、時がそれを許さない。現実がどうしたって、許さない。それ以前に、俺はまだ、ちゃんと眠れそうにないのだ。
どこか遠くに行きたい。足場さえなくなってしまうような、そんな場所へ。それは今一番求めていないことだろうけど、それぐらいのギャップの方が、まだ納得できるような気がした。
俺は少し混乱しているのかもしれない。いつも襲ってくる、罪悪感というか、そういうモノのちょっと手前で、俺は興奮だけを弄んでいるような、そんな感じだ。
それは、まだ、自分の考えや主張に、強くしがみついていられるってコトだ。
そしてそれは、誰にも邪魔されたくない、って事だ。
でも、現実は、本当に残酷だ。
俺は踊り場を半回転して、階段を上りきる。一番奥から二番目のドアが、俺の部屋だ。
そこで俺は、人影を見た。ドアの前に佇む人影を。
それはもう、何度も見た光景で、何度も触れたラインで、よく知った顔だった。
桜子だった。
俺は桜子の存在を一瞥した時に、自分でもわからない衝動に駆られた。
次第に引いていこうとしていた興奮。代わりに顔をもたげようとした自己嫌悪から来る罪悪感。それに繋がって、もみくちゃになっているあらゆる事象の糸。
それらが急にピンと一直線に張りつめた。反動でとても純粋なトーンで震える。
そしてそれは、俺に恐ろしい顔を見せた。
俺が見つけたのは、すべてを複雑にする陰の存在。犯されたくないモノを、好き勝手に浸食したり離れたりする存在。信頼の前提であるすべてをさらけ出すことを拒否した存在。
今の俺にとって、考えるだけでも恐ろしかったはずの、拒否。
すべてが一瞬ではじき出した答。俺が最低になる方法。誰もが抱いている、希望を壊滅させる最善の方法。
俺は静かに一歩踏み出した。
桜子は俺に気が付いて、こちらを振り向いた。
二歩目はまだ躊躇して、スピードを鈍らせる。
桜子がどんな顔をして、俺を見たのかは覚えていない。
三歩目がコンクリートを蹴った。
その瞬間の顔は、さすがに俺は見ていられなかった。
スピードを付けて、俺は桜子に右拳を振りだした。運動が得意ではないし、何かを習っていたわけではない。
でも、その一直線の矢は、確実に桜子の右頬を捕らえた。
鈍い音がした。振動が、胸板を奮わせる。
俺は悪魔の声を聞いた。